CASES
イワイ株式会社様
リーダーグループコーチングご利用 ― イワイ株式会社様 ―
「仮想の会社」に取り組む中で見えた、自社の課題
Q. 今回の1クール・全5回のグループコーチングには、10名がご参加されていましたね。プログラムは、参加者がチームに分かれてそれぞれ擬似的に「会社」を作り、相手の会社の問題点を指摘し、改善案を提案する「コンサルティング」を行う流れで行いました。社長は、最後の回で、2チームそれぞれから、1クール目の最終課題である「プレゼン」を受けたんですよね。

はい。そうですね。改めて振り返ると、今回のプログラムで用いられた「相互の会社のコンサルタントとなって課題解決を行う」というソリューションが非常に素晴らしかったと感じています。このプログラムは、「架空の会社をテーマに、その会社の問題点を挙げる」という話からスタートします。ただ、その架空の会社というのは、結局のところやっていくうちに「自社」のことになるんです。
「課題はこれですね!」と出てくる問題というのは、実はまさに今の自社の問題点なんです。中にいる人たちが腹の底で問題だと思ってることが湧いて出てきて、その問題点を指摘した上で、さらにそれに対して外から指摘・改善提案をするわけです。「この会社のここを変えるべきですね!」と。
なので、結局やったのは「客観的に、外からの目でうちの会社を見て、問題点を提案しよう」というカリキュラム。
仮想として思いっきり指摘して提案してコンサルして「何をすべきか」を突き詰めていく先が、結局時自分たちの現状に対して言っていることになり、全部ボールが戻ってくるっていう。この仕組みが素晴らしい。おそらく参加者は、プログラムに取り組んでいる間、現実と仮想の狭間にいるような不思議な感覚だったと思いますよ。
この仕組みの何がすごいかというと、「それを変えるのは誰なの?あなたたちでしょ?」と全部ブーメランで返ってくるわけなんです。これは「自分たちで本質的な課題に取り組まざるを得なくなる仕組み」なんだと思っています。
今回、仮想のプログラムを進めていった結果、2チームとも結局は現実の同じところに辿り着き、「イワイ株式会社の課題はここだよね」と、現実での合意が取れたわけです。
私がもし「社長がいないと回らないのは問題だから何とか変えてくれ」と言っても、こうはならないんです。彼ら自身がその問題点を認識して、意識して、提案を煮詰めてくるからこそ、彼らはやらなきゃいけなくなる。この仕組みがすごいなと思ってます。
Q. 仮に同じ「課題」と「解決法」だったとしても、外の誰かに言われても違うわけですよね。自分たちで見つけて、自分たちでこれだって突き詰めたものを、結果として自分たちで持って帰り、向き合い続けるということですよね。
次は「マネージャーとは何なのか」に向き合っていく
Q. これから、第2クールがスタートします。次のクールではどんな変化を期待していますか?
ここまでの「コミュニケーションの変化」や「社長不在でも動くマネージャーへの変化」を、さらに強化することが重要です。そのため、次クールのテーマである「マネージャーとは何なのか」に取り組む必要があります。

第1クールで、自分たちで課題を理解し、変わらなきゃいけないことも主体的に動いていくべきということもわかった、と。じゃあ我々は何をしなきゃいけないか、というのを具体的にまた彼ら自身も考えて出していくというものです。
今までももちろんマネージャーの要件定義というのは私がある程度言語化して伝えてはいます。でも、次のプログラムはまた彼ら自身が、「マネージャーとはなんなのか」という問いに向き合い、皆で合意を取り、自分たちがどうしなきゃいけないのか突き詰めていく、と。そして、言ったらまたやんなきゃいけない、という。
なので、また、間違いなく変わると思います。自発的に変わっていくと思います。
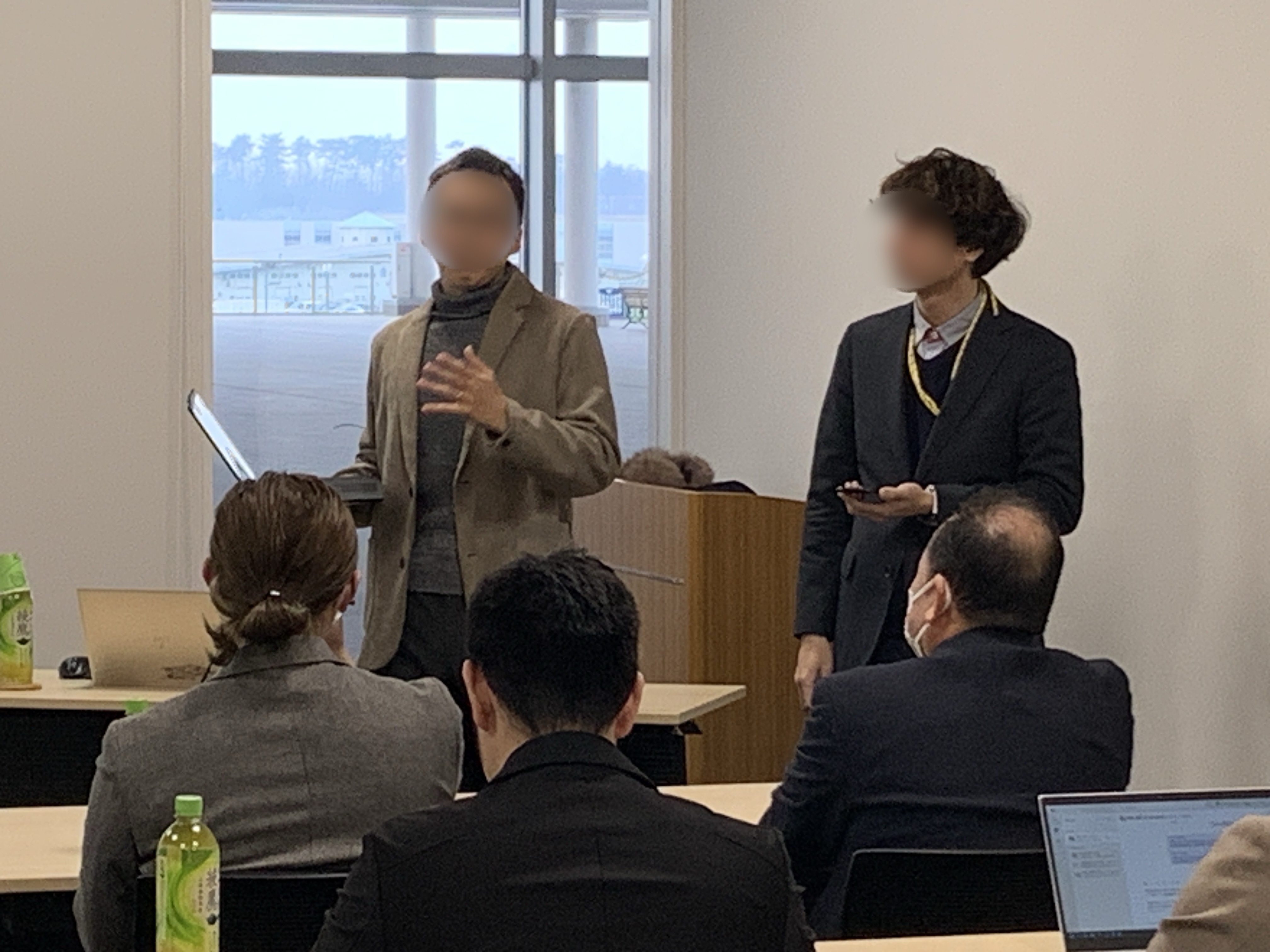
先日、改めて参加者たちに「これは会社として大事なプロジェクトで、この中でやるものはファンタジーの話じゃなくてリアルなんだ」と話をしました。つまり、プログラムの中できちんと要件として決まって、それが本当に報酬につながるものであれば、リアルでも報酬も上がっていきます。そういった制度設計にもこのプログラムが連動していき、会社の組織を作っていくわけですね。まずは組織の要件定義、その先に評価制度という話になっていくのかなと思っています。
本気で取り組めば、必ず動き出す
Q. このプログラムを検討している方へのメッセージをお願いします。
こういったプログラムは、事前に具体的な成果をイメージするのが難しいものです。「このテーマで、こういう流れで進めます」といった型通りの内容ではなく、最初から結果を予測できるわけでもありません。

ただ、事前に感じていた課題があり、それがまさに浮き上がるような組織診断の結果が出ました。その結果や、参加メンバーとの1on1を踏まえた上でプログラムを組んでいただき、スタートしました。
組織診断は脳科学ベースで「この組織の点数が何点です」「〇〇が弱いので強化しましょう」といった単純なロジックではありません。そのため、すべてを理解できたわけではありませんでしたが、方向性や概念について丁寧に説明いただき、「覚悟を持ってやりきろう」と決めて委ねました。
私は脳科学の知識があるわけではないので、このプログラムの仕組みをすべて人に詳しく説明できるわけではありませんが、車を運転するときに車の仕組みをすべて理解していなくても乗れば動くのと同じように、このプログラムに真剣に取り組めば変化がある、と言えます。
課題があり、その明確な対処法が見つかっていないのであれば、このプログラムに取り組む価値は大いにあるはずです。
「車が動く!」と1クール目で実感した参加者たちは、次のクールを楽しみにしていると思いますよ。
【前編】「行動変容」で成果を測る─―主体性を育むプログラムの価値
前編へお気軽にご相談ください
専門的見地から定量的に可視化したストレスデータを元に、組織内に起こりうる課題を分析し、組織の生産性向上、チームマネジメントの改善、メンタルヘルス環境の改善などに向けたソリューションを実施します。