CASES
イワイ株式会社様
リーダーグループコーチングご利用 ― イワイ株式会社様 ―
「トップダウン型から自律型の組織」へ。変革の歯車を動かしたプログラム
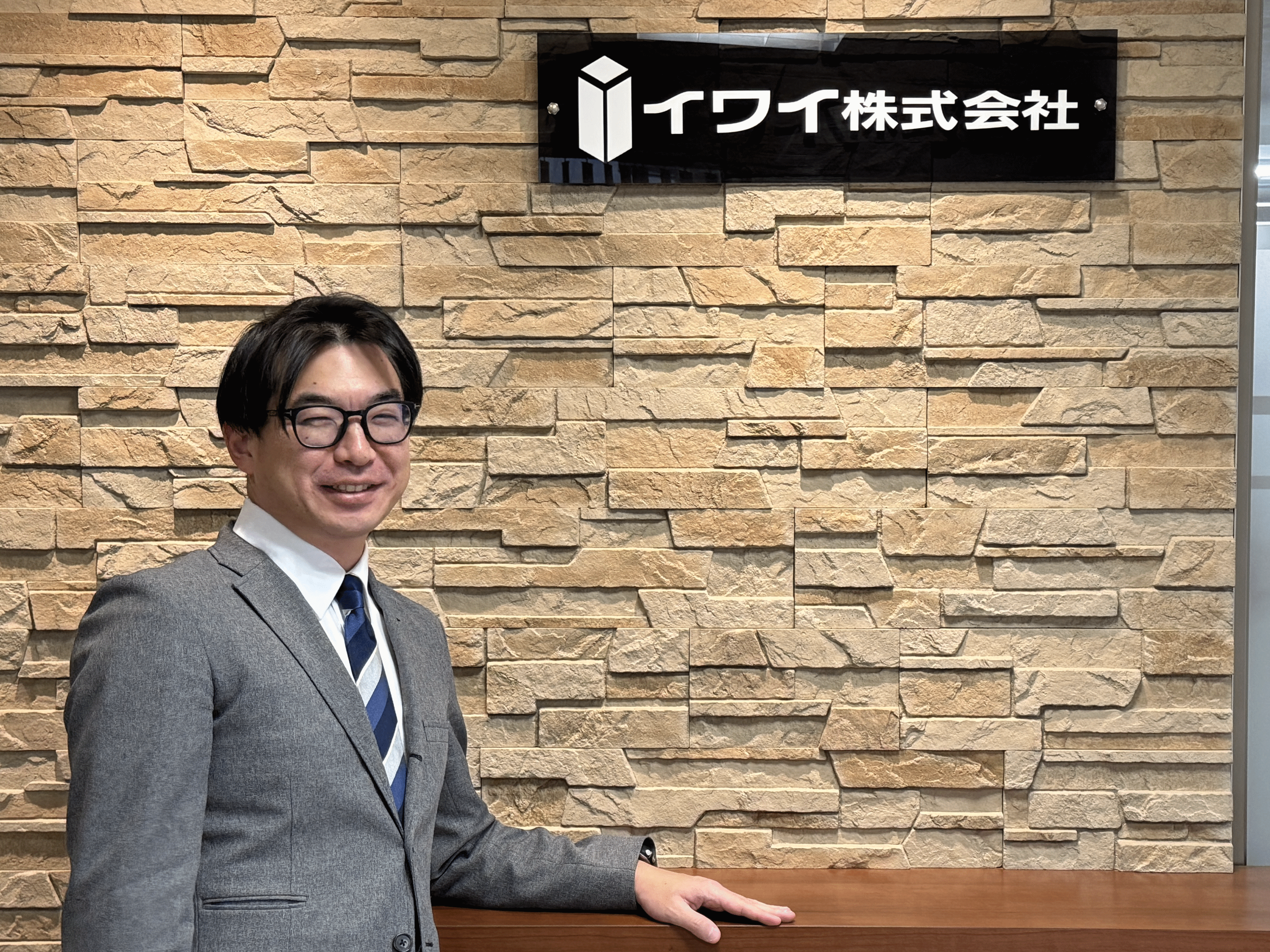
岩井社長
コミュニケーション不足、部門間の軋轢、マネージャー層の育成課題……。イワイ株式会社が抱えていた課題は、多くの企業が直面しているものと共通していました。これらの課題に対し、「社長不在でも自律的に動く組織」を目指し、あるプログラムを導入した結果、変革の歯車が動き始めました。
「今回のプログラムは、過去の取り組みと比べてもトップクラスの変化を生みました」と語る社長。
その変革の鍵を握ったアプローチとは。イワイ株式会社の課題から成果までのプロセスを、2回にわたる記事で紐解いていきます。
サマリー
▶課題
- トップダウン型構造による、マネジメント力の不足
- 働き方の多様化に伴うコミュニケーション不足・部門間の連携不全
▶実施施策
- 脳神経科学的アプローチによる組織診断
- 全参加者との1on1セッション
- 参加者10名/月1回・5時間の「課題発見・解決型」グループコーチングプログラム(計5回)
▶成果
- 主体的なコミュニケーションの大幅増加
- 参加者の他者評価による行動変容
- マネージャー層の視座と行動の変化
- 非参加者への波及効果による組織全体の活性化
検証したのは「意識ではなく行動まで変わったかどうか」
Q. 早速ですが、1クールが終わってみての率直な感想と、社長としてどのようにこのプログラムを「検証」されたかをお伺いできますか?
まず、最初に、このプログラムを通して非常に大きな変化があったと感じています。過去に当社が受けた研修やプログラムの中でも、トップクラスに影響があったものでした。
開始当初は、参加者には「管理職としての視野拡大」や「発言や行動に主体性が出ること」を期待していました。そのため、検証として重要視したのは、知識やスキルの習得ではなく、「行動が変わったかどうか」という点です。アンケートで「意識が変わりました!やる気が出ました!」と言っても、実際の行動が変わっていなければ意味がありません。そういう観点で見ると、当初望んでいた2点(マネジメント力アップとコミュニケーションの向上)は、どちらも変化が見られました。
まず感じたのは、行動が変わったこと。
その変化というのは、私から見て変わったというだけではなく、チームで検証しました。
やり方としては、座談会を実施し、その中でそれぞれにアンケートを行いました。「自分が変わった点」についての自己評価に加え、「他のメンバーが変わったと思う点」という他者評価の項目を入れ、そういった変化について、他のメンバーがそれに同意するかどうかもも含めて検証したんですね。
つまり、Aさんが「私はこう変わったんです」と言っても、周りのB、C、Dさんが、「いや、あなた変わってないよ」ってなったら、それは自分で思ってるだけ。でも、「私はこう変わりました」に対して「確かにそうだね」とB、C、Dさんが言ったとすれば、それは本当に行動が変わったと認められますし、もし自分が変わったと思ってなくても周りから見て変わったのであればそれはやっぱり変化だと思うんです。
この座談会で、実際「変わっている」というポイントが非常に多く挙げられたことで、変化が大きかったという判断をしているというところです。
Q. そのように検証をされたんですね。具体的な変化をお伺いする前に、どのような背景・課題があったのかお伺いできますか?
どうせやるなら、対策までセットのプログラムじゃないと意味がない
最初にこのプログラムについての話を聞いたのは1年半くらい前で、もともとはとても信頼している方からの紹介でした。
当時の状況としては、何年か前から売上や利益のような数字で測れるもの以外の指標に注目しており、「やる気」や「モチベーション」など、数値化しにくい要素をどう評価するかを考えていました。それに対する取り組みとして、一度は「エンゲージメント」の概念を取り入れ、エンゲージメント測定を行ってみたのですが、良い結果は得られませんでした。分析に納得感もなく、そこで見えた課題に対し自分たちなりに社内で施策などを打ってみましたが、それも今ひとつ成果には結びつかなかったんです。
組織診断系もいろいろと調べてみましたが、調査だけというものが多く、「現状や課題がわかったとして、じゃあそのあとはどうするんですか?」、と。診断、それから原因、そして対策までがセットでなければ意味がないな、と思っていた時に聞いたのがこのプログラムでした。
「社長不在では進まない組織」をどう変えるか
社内の課題というのはその時々の会社の成長段階に応じて出てくるものだと思いますが、当時の当社には大きく2つの課題がありました。
一つは、組織内コミュニケーションの不足。リモートワークや直行直帰など働き方改革の推進が進んでいく一方で、コミュニケーションが如実に減っていました。これはエンゲージメント調査結果でも出ていたので、先にも述べたように、社内施策としてコミュニケーション向上に向けていろいろとやってみましたが、解決には至りませんでした。
もう一つはマネジメント力の向上です。私は基本的にトップダウン型でやってきており、「社長の意思で物事はきちんと進む、一方で社長が不在だと何も進まない」という状況に課題感を感じていました。
どちらもこのままではいけないし、何か手を打たなければいけないのは明白だったので、信頼する方からの紹介であれば、覚悟を決めてやってみよう、となりました。
「会議室が埋まり、提案が生まれた」目に見える変化の数々
Q. では、具体的な変化について教えていただけますか?

今回、大きな課題として挙げていた「マネジメント不足」と「コミュニケーション不足」のうち、特にコミュニケーション不足に関しては、「能動的な打ち合わせ」が目に見えて増えました。
社内の応接室やミーティングルームなど、いくつかある打ち合わせ場所の利用率が大幅に上がりました。
これは、何も「会議が多い方がいい」ということではなく、これまで主体的なコミュニケーションを避けていたところから、具体的に大きな変化があった、ということです。みんなが望んでやっている会議や打ち合わせなので、向き合い方、合意の取り方が明らかに変わったと感じます。
もう一点、「マネジメントの向上」について。これまでなんとなく「社長がいないと…」という暗黙の了解・不文律があった中で、このプログラムが終わる時、参加者たち自身から「それを打破していくんだ」という方向性が明確に示されたんです。この課題が、社長の私が把握している課題ではなく、全体の向かう方向として共通の認識になったわけなんですよね。この「共通の認識」というのはすごく大きくて、各種会議でも「社長が居なくてもできるようにしなきゃいけない」「いないと動かないっていうのはまずい」と自然に出てくるわけです。
例えば会議で私が発言をすると、「いやいや、社長がそれ言っちゃったら社長がいないと進まなくなりますよ」「社長、そこは出てこないでください」と指摘を受けることも出てきました。
他にも、これまでは社長ありきで、会議の開催は私がマネージャーを召集するのが常でしたが、マネージャーたちが自発的に打ち合わせをして、私へ提案を持って来たりしました。これは大きな変化だなと捉えています。
Q. 実際に参加した方々からの声も変化が見て取れますね。
- 主体的な発言や行動がそれぞれ増えた
- コミュニケーションについて発信の仕方や受け止め方も変わり、返す言葉も変化した
- 「グループワーク」に真剣に取り組む中で「共通言語」ができたことで距離が縮まった
- プログラムを通して、相互理解が進み、自分が動けば変わる、重い歯車が少しずつ動くと体感できた
- 組織が円滑に進むためのマネジメントを意識し、多角的に物事を捉えられるようになった
視座が変わり、重い歯車が動き始めた
実は、今日このインタビュー予定をカレンダーで見た参加者から「今日、miloqsさんと話すんですか?」って聞かれたんです。「なんで?」と返したら、「ぜひ社長からお礼を言っておいてほしい」と。
実は、今回の参加者には技術者チームのメンバーがいたんですが、技術者同士ってすごい論争が起きるんですね。もちろん好き嫌いではなく、物事を決めていくにあたって、「これはこうすべきだ」とか「こうじゃない」とか。主観によって激論に発展してしまうケースもあったんです。

そんな様子を見ると、周囲はどうしても見て見ぬ振りをしたり触らぬ神に祟りなしの状態になってしまったりしていたんですが、彼ら曰く「このプログラムを受けて、感情的なだけのやりとりになるようなことが減ったんです」と。「コミュニケーションがきちんと取れるようになって合意が取りやすくなった」と言うんです。
きっとそれは、双方向の話だと思っていて、プログラムを経てコミュニケーションの受け取り方も発信の仕方も変わっているはずで、結果として、そうなってると思うんです。そしてそれをこのプログラムの成果だと本人も理解をしているわけですね。これは間違いなく成果ですね。
Q. コミュニケーション不足に対して、「仲良くなる」「雑談が増えた」とういうようなことではなく、より良いものを作っていく、よりレベルの高い組織を持っていく、との視点で成果として出ているのが素晴らしいなと感じました。
そうですね。それでいうと、やはり、プログラムを通じてコミュニケーション力を身に付けたと同時に「視座」も上がったことが原因だと思います。今回の擬似会社を経営する立場でのプログラムを通して、普段の業務とは違う視点を学んだわけですよね。
プログラムの後、参加者たちに「いやー、社長って大変ですね」「社長ってこんなこと考えてるんですね」「可哀想になりました」と言われました(笑)
【後編】「自分たちで課題を見つけ、自分たちで解決する」――主体性を育む仕掛け
後編へお気軽にご相談ください
専門的見地から定量的に可視化したストレスデータを元に、組織内に起こりうる課題を分析し、組織の生産性向上、チームマネジメントの改善、メンタルヘルス環境の改善などに向けたソリューションを実施します。